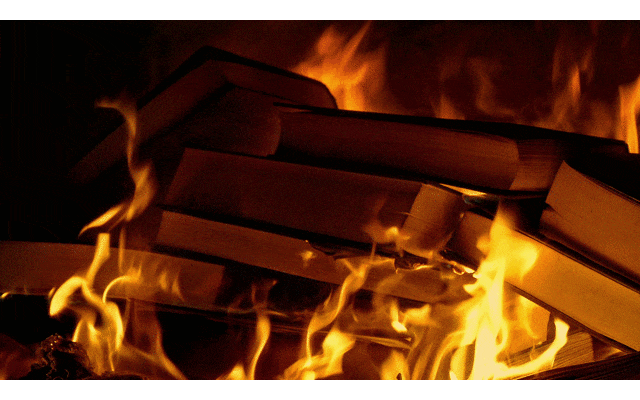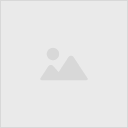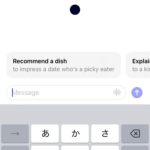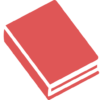これ、GPT-5 Thinkingの的確なWeb検索が使えるようになってから、研究アイディアの壁打ちはレベル1つ変わった印象です
「自分の専門ど真ん中」と「かじった領域」の掛け合わせとかも有効と思いますが、かじった領域の知識がGPT-5の方が私より強すぎて付いて行けない事もあります😅 https://t.co/Ro4JhRAvvJ
— 限界助教|ChatGPT/Claude/Geminiで論文作成と科研費申請 (@genkAIjokyo) September 25, 2025
AIの以前・以後で、
研究環境は大きく変わりました。
なぜなら、
思考の一部をAIに分業できるようになったから。
今まで10必要だったのが、3になる。
だから、自分は新しく7ができる。
で、新しい7の仕事も、
多くはAIにお任せできる。
すると、また次のアイデアを試せて・・・
成果の創出がめっちゃ早いのです、
AIが進化してからの研究って。
本当に、早い。
ご存知の通り、
海外の論文もAIにぶち込んで、AIに欲しい情報を聞けば、
一瞬で欲しい情報に辿り着けますし。
そもそも、その論部でさえ、
AIに見つけさせるのが、今の流行りですし。
かつての、いちいち論文を検索して、
なかなかヒットしなくて、渋々大学の図書館をさまよって。
欲しい情報が出てくるまで、たくさん読んで。
やっとそれっぽい論文に出くわして。
詳しく読み込んで、言ってることをちゃんと理解して。
やっと欲しい情報が手に入る(確定する)ってのが、
これまでだったのですわ。w
ああ
めっちゃ時間かかるでしょ?
それが今や、AIに聞けば、かなりの精度で欲しい論文が出てきて。
その論文を「読む」作業さえ、
半分以上をAIにお任せすることができる。
それが、現代です。
現代というか、ここ1〜2年ですね。
ここ1〜2年前くらいから、
AIのレベルが、研究に耐えうるレベルになった気がします。
まあ、言ってもできることって、
論文を調べたり、訳したり、解説してもらったり。
計算用のコードを書いてもらったり。
そのくらいなんですけど、ね。w
でも、それでも、
研究成果を上げるまでの時間は、格段に短くなっている。
AIを使っている研究者の、
成果を上げる早さが違うのですよ。
早すぎる。
論文検索とか、計算プログラムの組み立てとか、
そういう外注できるような雑用
に振り回されなくなった分、ですね。
成果のサイクルが早いのです。
それに、かなり楽。
自分は、研究の方向性と、
「何がやりたいか」
だけ考えていればいいですから。
全体像は自分で引く。
それを進めるための、
細かな雑用は、すべてAIに押し付ける。
それが、今の研究。
最先端の研究スタイルとなっています。
#AIは雑用係
#成果サイクルが早いってことは、世代交代が早いってこと
#30〜40歳の研究者を、数年で追い越せる。
#その分野のトップに立てる
#と、いうことは・・・言うまでもなく美味しいですよね?