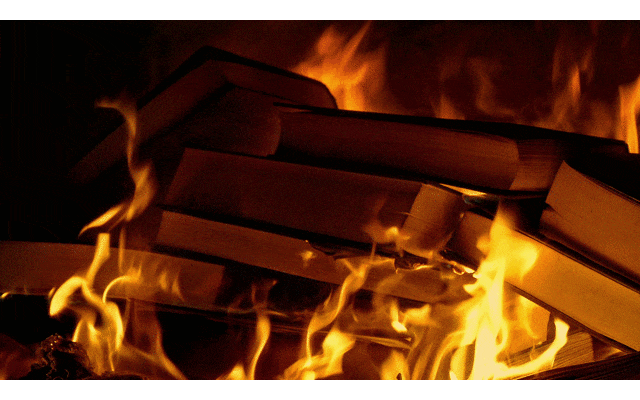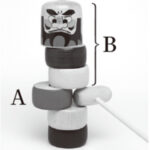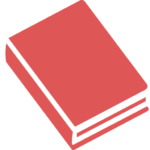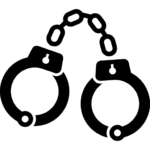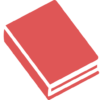これちゃんと理由があってね。世界的にみて日本って紙が異様に安かったのよ。
雑に現代の価格にすると和紙は「1枚10円程度」
比べて西洋の羊皮氏は「1枚4000円程度」
文字/記録文化が庶民のものか貴族のものかが圧倒的にここに出る。 https://t.co/7gnuQgcOxm
— 新野ユキ (@yuki_arano) March 27, 2025
和紙の発明(中国からの技術輸入)
それに伴う、庶民の識字率増加。
歴史文化と技術はつながっている。
なので庶民が適当に書いた絵とか日記とかが結構残ってるのよね…数が多いから
あと間違いなく江戸期の識字率の高さにも影響しているだろうし…
— 新野ユキ (@yuki_arano) March 27, 2025
西洋だと紙にできる原料がなく、
木材パルプの発明が必要だったらしい。
他のエピソードだと、中国・唐の時代の太宗は20万冊の書物を保有していたが、同時代のローマ教皇はせいぜい数百冊だったなんても有名だねぇ
— 新野ユキ (@yuki_arano) March 27, 2025
装丁の豪華さや、書物の冊数にも影響。
キリスト教が崇められたのは、
読み書き技能を実質聖職者が独占していたから(らしい)
(聖書の保有が識字技能の評価になっていた?)
18世紀までは東アジア…というか中国と日本の情報流通量が圧倒的だものね。他の世界と比べて。
7世紀の唐の図書館と欧州最大のバチカンの図書館の蔵書数は1000倍以上の差って話はこれ関連でよく出てくる。
欧州とかだと中世までは読み書き技能を実質聖職者が独占してたのも大きいし。— それでいいよ (@kfGWK64UPnzLiZG) March 27, 2025
和紙の価格については、要検討。
そうですよね。戦国時代に「紙で尻を拭いたので、身分の高い人間だとバレてしまった」みたいなエピソード聞いたことあります。さすがに10円はありえないのでは?
— ますだじゅん@『5分で読書 未知におどろく銀河旅行』発売中! (@CRwVUTh6Xjn2eG8) March 27, 2025